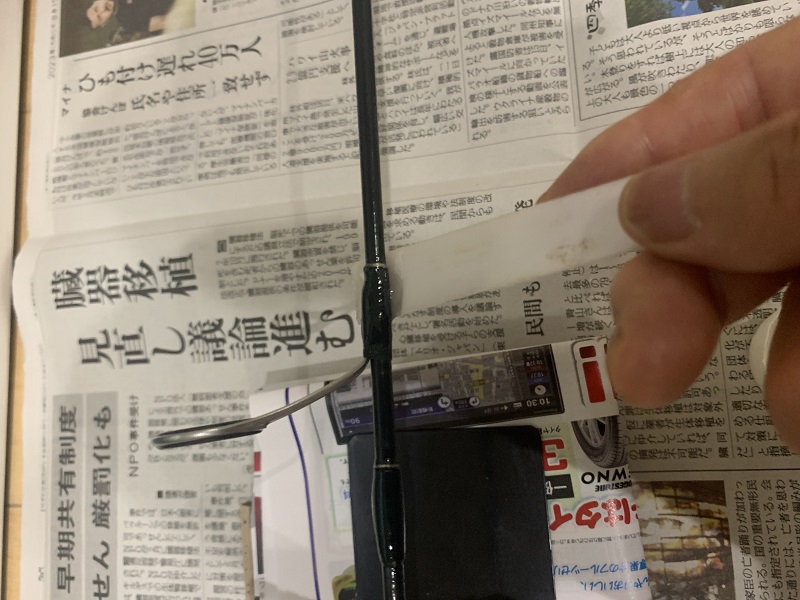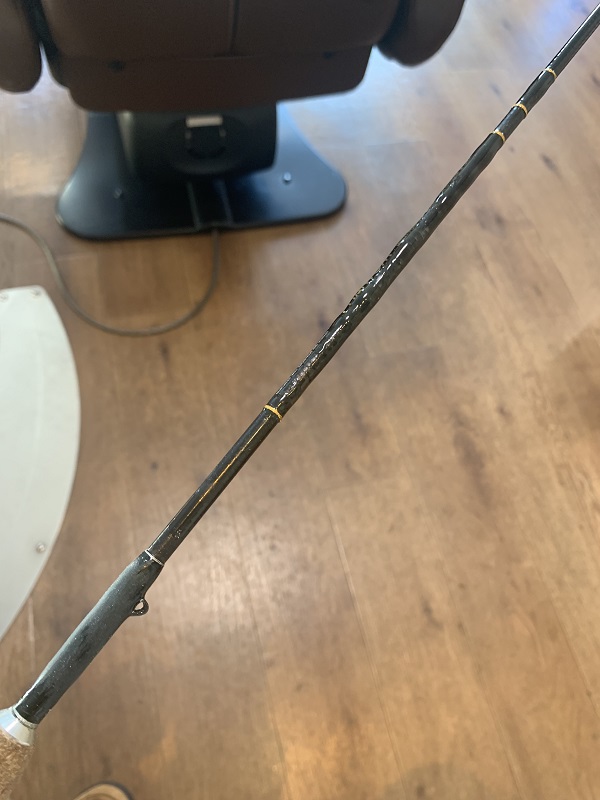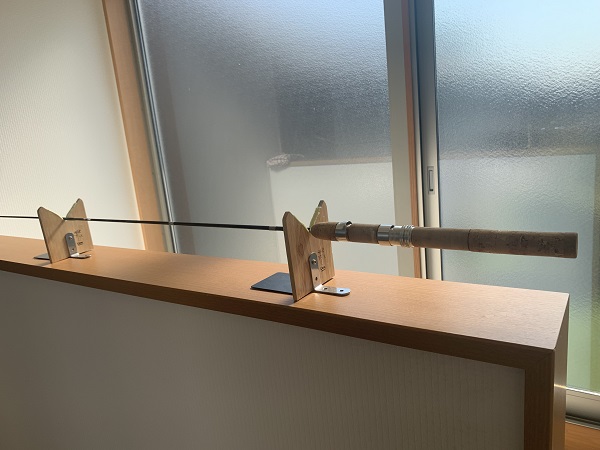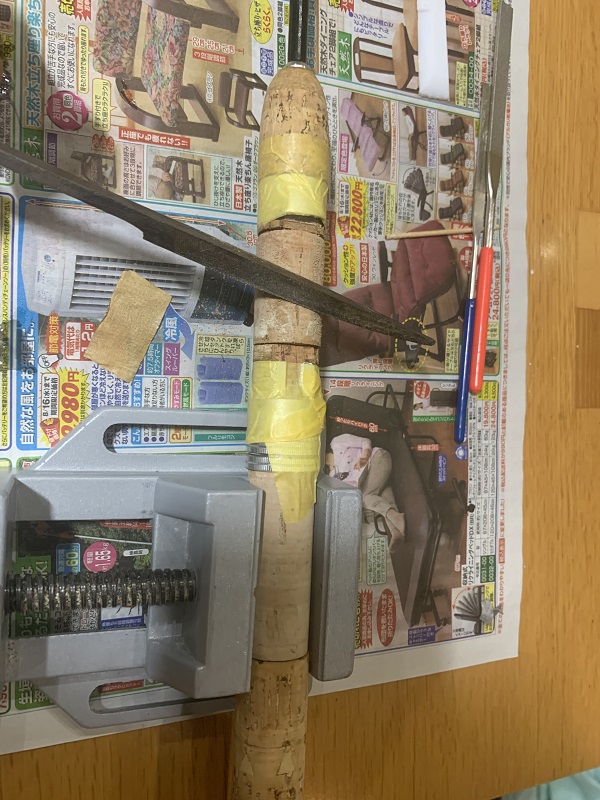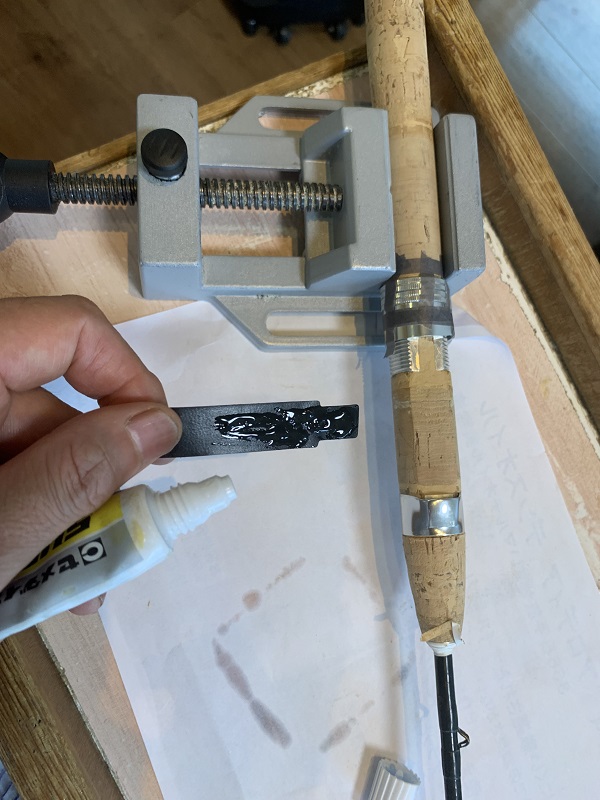12月に入ると諸用で忙しくなります(;´Д`)
釣りに行けるどころか
オフシーズンに入っているので
ハイシーズンでは手が付けづらいハンドメイド系に
手を付けたいのですがなかなか作業は進みません
(-_-;)
10月に中古で購入して
11月にカスタムし始めたロッドがありました

川路のC&Rに持って行って使用してみたら
ミノーはいいかもしれませんが
スプーンの飛距離が厳しいと思い(汗)
ガイドをカスタムすることにしました

時間があるときに付いていたガイドを外して
8個から7個に変更(飛距離を出したいので)
一番手元の25mm径のガイドをHIGHガイド
(高さがあるガイド)にして
糸抜けしやすくしようとガイド変更をしました

元のガイドが写っていませんが
高さがある分だけ手前に持ってこれるので
バットの固定に大いに役にたってくれます
それと購入した根元に近いガイドはステンレス製
元からついてるガイドは
チタン製の高価なものでしたが
手前に近くなるほど持ち重りが感じなくなるので
大丈夫だろうと投入してみました

ガイド位置を固定して
スレッドを巻いていきます
実際に思った以上に持ち重りの心配がなかったのは
良かったです^_^;

一回目のエポキシ塗りです^_^;
薄くつけてガイドを固定します

ちょいアクシデントが(-_-;)
根本近くのガイドを位置決めしてる
最中に隙間ができてしまい
分からずにエポキシでコーティングしたら
ガイドの根本までスレッドが巻ききらずに
固定不完全な状況になってしまいました(~_~;)
スレッドを足して根本近くまで持っていき
巻き直しの箇所に再塗布して塗り直しです( ;∀;)

だいたいある程度エポキシで固めた後に
川治に行って確かめてみました ↓
晩秋を感じながら川治のC&Rに行って来ました(^^♪ – ヘア&リラクゼーション Maverick
で、釣りして感じたことがありまして
ガイドの位置決めで根本に持ってきた
ガイドの抜けは問題ないのですが
ルアーが思った以上に飛ばない(-_-;)
原因は何か考えてみました
トップガイドの径が細く感じていたのですが
元のガイド径が5mm
個人的には6mmにしたかったのですが
元からついてるガイド径の兼ね合いもあって
5.5mm径の大きさのガイドを注文しました

写真では わかりづらいですが
上が5mm内径で
下が5.5mm内径
写真では分かりづらいですが
肉眼ではハッキリと大きさが違います
6mm径にしなかったのは
先重りが怖かったので(-。-;
ロッドもガイドの大きくなれば
ガイド抜けがいいのですが
単純に重くなりやすいです(汗)
今時のルアーロッドはガイドの傾向が
小口径で多めに付いている様な気がしてます
(あくまで僕主観が入った考え方ですが)
ロッド扱いづらくなると
釣りが難しくなってしまいます

先端をライターであぶってペンチで取ります
この上からスレッド巻きなおして
エポキシを再度塗り直します
その後に元から付いていたガイド跡を
消すためや
紙やすりでガイドを削り直しては
エポキシコーティングし直して
ロッドを仕上げていきます

ロッドを購入した際に
ロッドカバーを購入しました
親切な店員さんがいて
一緒に探してくれたんですが
丁度良い長さが無くて
購入した物も長さが少し足りませんでした

どうしても先端が出てしまうので
マジックテープの位置をずらします
更に縫い付けて元からあったマジックテープには
干渉しないように上から重ねてマジックテープを
張り付けします
新しくマジックテープを縫い付けて
完成させました
(作業的にこれも結構しんどかったです)(@_@;)

わかりづらいですが(;^_^
ガイドの付け直しが完成です
忙しくて試し投げは出来ませんでしたが
もうこれで慣れていこうと
心に決めましたσ(^_^;)

ガイドのエポキシ塗布も
いまだに慣れが必要な感じですが
頑張った分だけちょっとづつ上手くなったような?
気がしてます(^^♪
錯覚だっていいんです(^▽^;)
メーカーさんならもっと絞り込んでいくんでしょうが
僕の素人ロッドメイキングではこれが限界なので
「お前と一緒に!」と決めました
↑ なんか「演歌」のフレーズみたいに聞こえます
気のせいでしょうか(^▽^;)
来年は時間を見つけて
川治で試し釣りが出来たらと
思う今日この頃です
これから大みそかに向けて
皆さんも寒い中
色々と忙しいと思いますが
とりあえず僕の今年最後の投稿になります
(趣味の方ですが)
今年一年間お付き合いくださって
ありがとうございました<m(__)m>
来年も飽き足らず(?!)
お付き合いの程 よろしくお願いします(^^♪
平野 敏之